ジブリ作品で有名な宮崎駿監督が描いた、黄金の実をめぐる一人の青年の冒険を描いたのが、本作「シュナの旅」です。
黄金の実は、我々の世界の穀物に似ているのですが、その黄金の実を求めて、緑色の巨人や大きな顔の月と出会い、人買い族と争う様子は、見ていてとても引き込まれるものがあり、作品全体の構成がとてもよく出来ていて面白く、完成度が高い作品だと思いました。
私達が普段生活している世界について、日常に満たされている大切なものについて、今一度考えさせられるような、しかも、それを指導的に押し付けるのではなく、壮大な物語を通して、思い起こさせてくれるような、とても大切な事が描かれている一冊だと思いました。
シュナの目指す黄金の実とは何か

このマンガでは、主人公のシュナが、黄金の実を求めて各地を旅する様子が描かれていますが、黄金の実というのはそもそも何なのでしょうか。
おそらく、この世界特有の穀物だと思われるのですが、我々の世界に当てはめて考えてみたら小麦などがそれにあたるでしょうか。
シュナの前にも、黄金の実を求めて旅していた旅人がいましたが、この世界では、黄金の実の種子は貴重な存在であるようです。
黄金の実の種子は、どこにも売っておらず、手に入れる事ができません。
そして、この物語は、黄金の実が広く行き渡って普及していく過程を、一人の旅人シュナの冒険に当てはめて描いているのではないか、と思いました。
黄金の実が豊かに広がる前の世界では、黄金の実を得るために多大な努力がはらわれます。
そして、黄金の実が行き渡るようになると、その他の豊かなもののために努力が払われ、それが普及し、世界は発展していく。
この物語からは、そのような構図を見てとる事ができます。
小麦の開発と大量生産、テレビの発明と普及化、など、日常生活に様々な物資が普及していく過程を知る事は、歴史を知る事でもあると思います。
教科書では、それらの発明や普及は、一行の文章でしか描かれていませんが、その背後にある歴史の過程を考えてみる事で、それぞれの製品、サービス、制度の成立には、様々なドラマがあったのだ、という事が見えてきます。
そして、その事によって、より深く世界を理解できるのではないか、と思います。
黄金の実をめぐる争いと苦労の数々

昔の日本、特に戦後は、食べ物も自由に食べられず、お腹を空かせた人々がたむろし、米などは政府からの配給に頼らざるを得ないという時代もありました。
現在、私達は、特に意識せずに自由に米を食べていますが、昔は、そのような米が食べられない困難な時代があったのであり、経済が成長し、日本が豊かになり、その結果、今豊かな生活を送る事ができている、という事は、押さえておくべきポイントだと思います。
そして、現在の生活の豊かさを再認識する上で、このマンガはその一助となったような気がします。
それでは、私達の生活の周りには、黄金の実はあるでしょうか。当たり前に存在する製造品の中に、これは、というものはあるでしょうか。
スマホは、2010年前後から大きく普及してきた製品ですが、それ以前は誰も持っていませんでした。
言わばこれが、最近の例における製造物の開発と普及の一例として考える事ができると思います。昔は、それが車やテレビ、冷蔵庫などであったのでしょう。
シュナが黄金の実を発見し、広げていったように、様々な製品が、様々な企業によって、広められていき、日本は豊かな物資に恵まれるようになりました。
スマホなどの贅沢品も、現在は特に意識せずに普通に使われていますが、それが普及していく過程や開発の苦労など、普及するまでの労力を思いつつ、現在の生活の豊かさを、時々でいいから考え、それに感謝できると良いのではないか、と思いました。
「シュナの旅」には、そのような身の回りの豊かさについて考えさせられる何かがあると思います。
古代文明は何を残したのか

シュナの旅のゆく先々では、超古代文明の残した遺物が多数残されています。
これほどの技術力を誇った文明が滅んでしまったのはなぜなのか。
その点については、一切説明されていません。
世界には、不思議な現象が数多くあり、巨大な顔をした月が夜空を飛んで行ったり、金属でも石でもない生体的な素材で出来ている黄金の実の精製器や、緑色の不思議な巨人など、物語の中には、その世界観を深める不思議な要素が多数満たされています。
そして、それらの存在が説明されていない事も、世界観を深める一助となっていると思います。
超古代文明が滅びているのに、金属でも細胞でもない、超常的な素材で出来ている黄金の実の精製器は、なぜ残されているのか。その点も気になります。
そして、それほど優れた超越的な技術が使われていながら、それが作り出すものが黄金の実という単なる作物である、というギャップにも考えさせられるものがあります。
超古代文明では、黄金の実のような作物は貴重な存在だったのでしょうか。
超越的な生物製造機のような優れた製造機があった時代だからこそ、作物である黄金の実は、貴重な存在だったのでしょうか。
そのような事を考えると、個人的には、どのような時代でも大切なものはあまり変わらず、それは、おそらく、作物や、人と人との温かい交流、豊かで穏やかな家族の時間、など、基本的でありながら疎かにする事ができないものなのではないか、と思いました。
金属と生物を融合させる超古代技術を持つ社会でも、黄金の実の作物が大切に育てられ重要視されていた、というのは、注目に値する事実だと思いました。
日常の中に潜む特別なものについて

このように、シュナの旅は、単なる娯楽マンガではなく、そこにある要素を紐解いていくと、様々な事を学んだり、考えたりできる、優れた一冊だと思います。
サンテグジュペリの小説「星の王子さま」において、5000本のバラが咲き誇る光景よりも、1本の特別なバラを大切に愛情をこめて育てていく事の重要性が説かれていましたが、これを、この「シュナの旅」に応用して考えてみてもいいかもしれません。
優れた便利なものが多数ある現代社会ですが、それを支える小麦などの作物のありがたさに気付く事ができれば、世界は豊かな色彩を持って見る事ができるようになるのではないか、と思います。
まして、小麦の流通と製造、普及化に多大な労力と冒険が費やされたのであれば、それに思いを馳せ、感謝する事ができるかもしれません。
このようにして、現代社会に広がる5000本のバラのひとつひとつに特別な思いを抱く事ができれば、日常は豊かに、華麗な色彩を持ってよみがえってくるのではないか、と思います。
「シュナの旅」は、娯楽マンガでありながら、このような、とても大切な要素を学ぶ事ができる優れた作品なのではないか、と思いました。







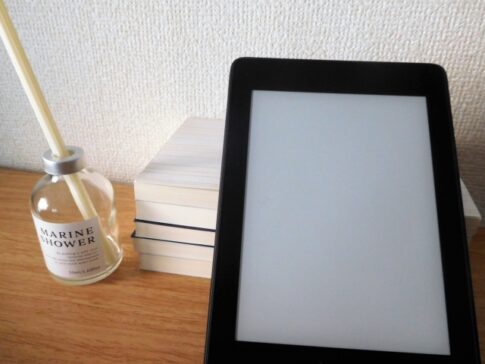














コメントを残す