「ギャグマンガ日和」は2000年から20年以上にわたって連載されているギャグマンガです。
タイトルにギャグマンガを冠することで極めて高いハードルを自ら設けていますが、そのタイトルに恥じない面白さを誇ります。
ネット上のレビューではおおむね好評のこの漫画ですが、一部の読者には全く刺さらなかったり、リアルでは語りあえる人は少ないなど必ずしも絶賛一辺倒の漫画ではありません。
そんな刺さる人には刺さり、合わない人にはとことん合わないこの漫画の魅力を紹介します。
目次
ギャグマンガ日和の魅力㈰ 豊富な語彙によるボケとツッコミ

ギャグマンガ日和の魅力のひとつは、ツッコミやボケに利用される語彙や日本語回しです。
通り一辺倒なやりとりではなく、極めて複雑な表現で会話がなされます。
一例として「どんだけ腹立つと思ってんだ」「どういう言語感覚なんだ」など、通常であれば「やめろ」「何言ってるんだ」のような簡素な表現をしてしまいそうなところを、上記のように婉曲的な表現を用います。
とても馬鹿馬鹿しいボケに上記を組み合わせることのギャップにより、妙なおかしさが生まれるのです。中には独特な世界観が表現され、私たちには極めて奇妙に映りますがその世界では自然なことである、ということを題材にする回があります。
その世界ではボケもツッコミもありませんが、奇妙な世界観の説明において同じように婉曲的な表現で大真面目に解説することによるギャップがおかしさを生み出します(便に似た成分ではあるが正確には何なのか断定できない、等)。
またはボケ側のキャラが自分の情けなさを言い訳にする際なども、いかんなくその豊富な語彙が効果的に働き面白さに繋がっています(仮に変態だとしても、変態という名の紳士だよ等)。
極めて馬鹿馬鹿しく時には下品ともいえるギャグから、語彙表現による作者の高い教養が垣間見え、ネタの質について信頼がおける要素となっています。
ギャグマンガ日和の魅力㈪ 一話ごとに異なる世界観

この漫画は一部登場人物と世界観が固定された回はあるものの、基本的に一話完結であり、毎回世界観が異なっています。
そのため前回の展開などに引きずられることなく、毎回新しい世界観による新鮮なギャグが提供されます。このスタイルにより、「世界観がそのままギャグで作中の人間はツッコむことがない」というような通常読み切りでしか提供できないギャグを、連載において提供できるという特殊な立ち位置を得ています。
必然的に「この回は面白い」「この回は合わなかった」などの当たり外れは大きくなるわけですが、毎回世界が違うというチャレンジによって最大公約数に刺さる面白さではなく、人ごとに異なる笑いのツボを深く刺すギャグを生み出すことができ、ギャグの大御所でありながら毎回実験的な面を持つ漫画となっています。
これは非常に興味深い要素で、ギャグマンガ日和の数多いレビューを見ても、一番面白かった回が人により全然異なっていたり、一般的には不評な回が自分にとっては大ヒットであるなど、ギャグのツボが人それぞれによって全く異なるということを感じることができます。
一方安定したギャグを望む読者の為に、一応続き物である「聖徳太子」「松尾芭蕉」や、オチが毎回同じである「うさみちゃん」などのシリーズを定期的に連載することにより、それらの層を取り込むことにも成功しています。
ギャグマンガ日和の魅力㈫ 偉人や名作、テンプレ展開をパロディする

聖徳太子や松尾芭蕉に代表されるような偉人をネタにする回は、怒りたくなるような要素もあるでしょうが、歴史が好きな人からはおおむね好評です。
伝記に書かれた偉人からは似ても似つかない性格だったり、世界観にそぐわないキャラや物質が唐突に描写されるのは笑いを誘います(飛鳥時代にカレーが存在するなど)。
ただハチャメチャな展開が起きながらも、最終的には何となく歴史的事実に着地する点等は、作者による歴史への誠実さを感じます。
シンデレラやブレーメンの音楽隊などの名作においても同様で、様々な要素をうまく料理して質の高い作品に仕上げています。
そしてギャグマンガ日和において白眉なのはテンプレ展開のパロディです。
少女漫画をパロディしたもの(絵柄も寄せている)、バトル漫画やスポーツ漫画をパロディしたものは数多くあります。
これらのパロディにおいては、その世界観にそぐわないものを最初に展開に取り入れることで、ギャップを生かしたギャグを生み出しています(少女漫画パロディにおいてヒーローが無職だったり、バトル漫画では精神攻撃を重視するなど)。
人気の「ソードマスターヤマト」などの漫画家シリーズは「テンプレ展開の作中作漫画とその筆者」をそれぞれハチャメチャな展開に巻き込むという二段構えのパロディであり非常にレベルが高いものとなっています。
ギャグマンガ日和の魅力㈬ ギャグに潜むホラー要素

「ホラーとギャグは紙一重」という言葉があります。
これは主にホラー映画などで、ホラーの表現が行き過ぎると(血が出すぎる、モンスターが大暴れしすぎる等)ギャグになってしまうということですが、ギャグ側からも同じことが言えます。
特にギャグマンガ日和においてその要素は強く、漫画に搭乗するアクが強すぎるキャラクターは、一線を踏み越えてホラーに足を突っ込むことがあります。
「木曽権次郎記念館」「ガラスのくつ」「キングダムキッド」「ファイティング戦士アベル」などそれを感じられる回は割と多く、普通の逆外でもわき役として登場するただ立っているだけのおじさんなどにもその要素があります。
馬鹿馬鹿しいギャグと気が抜けたような作画から突然表現されるホラーが、この漫画をより奥深いものにしています。




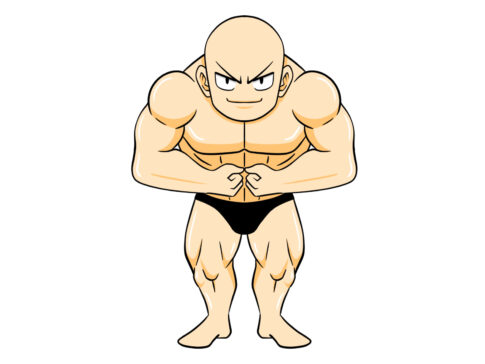
















コメントを残す